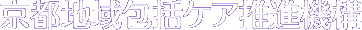- ホーム
- >
- 府民講座・イベント情報
- >
- ペコロスの母に会いに行く - 府民講座レポート
地域包括ケア 府民講座レポート
ペコロスの母に会いに行く
12月19日(木)龍谷大学アバンティ響都ホール

- 漫画家・シンガーソングライター 岡野雄一氏
- おかの・ゆういち1950年長崎生まれ。20歳で上京し、漫画雑誌の編集に携わる。40歳で長崎にUターン。父の死後、ゆっくりとボケていった母みつえさんと7年間同居。現在は週に2回ほど、母が暮らすグループホームに通う。2012年7月、母との日々を描いた『ペコロスの母に会いに行く』を西日本新聞社から刊行。全国で話題を呼び、16万部を超えるベストセラーに。実写版の映画も2013年11月16日、全国で公開。
平成25年度最後の府民講座は、認知症の母との日々を描いた漫画『ペコロスの母に会いに行く』の原作者、岡野雄一氏を招き、対談・鼎談の形式で行われました。同時に開催された漫画展の様子もお届けします。
- 第一部・対談「ペコロスの母に会いに行く」
漫画家・シンガーソングライター 岡野雄一氏 西日本新聞社出版部 末崎光裕氏
- 末崎
- 2012年7月に発行した「ペコロスの母に会いに行く」の編集を担当しました。今日現在で20万部売れています。
- 岡野
- 禿げ頭の息子が認知症の母に会いに行くというだけの話なんですよ。時代が切実になってきたということなんでしょうか。
- 末崎
- でも、もう人生で十分いろいろやってきたのに最後まで認知症におびえて暮らすのは嫌ですよね。私は岡野さんのマンガの編集担当をやって、自分の体験と重ね合わせながら、こういう風に考えてもいいんだと僕自身が安心させられました。
- 岡野
- 末崎さんもお父さんが認知症なのですね。
- 末崎
- そうなんです。岡野さんのマンガの読者からハガキをいただきました。その中で一番印象に残っているのは「母に会いに行く怖さが消えました」という内容でした。
母の人生を描いた「ペコロスの母に会いに行く」

- 岡野
- 僕は母が認知症になって、介護をするようになってから母のことをマンガに描くようになりました。
- 末崎
- それがこの漫画の主人公の母・みつえさんですね。熊本県の天草の農家に生まれ、長崎市の造船所に務める父・さとるさんのところに嫁いでこられ、岡野さんと弟さんを育てたお母さんです。
- 岡野
- その母とやはり認知症の叔父をモデルにした「エンドレスシアター」というシリーズがあります。認知症同士の会話で二人が「あの人」について語るのですが、どちらもその「あの人」が誰か分からない。
- 末崎
- 「あの人はどうしておられますか」「あの人ってだれ」「ああ、あの人。あんな目に遭って」「その人は誰ですか」「誰ってあの人ですよ」という長崎弁のやり取りのやつですね。
- 岡野
- 僕は、母の認知症の進行がゆっくりだったこともあって、病気という意識がなかったのですね。年を取るということは足腰が弱ったり、背中が曲がったりするように頭の中もそうなっていくんだと思っていました。認知症が進む母がなんかすごく愛しい、かわいらしいと感じていました。
- 末崎
- 「詫びる人」という作品では、亡くなったお父さんがみつえさんのところに「苦労を掛けた」と謝りに来るという話です。
- 岡野
- 母が認知症になって一緒に暮らしていた時、よく「さっきまで父ちゃんがここにいたよ」と言うようになりました。
「悪いことばかりではない」という希望の言葉

- 末崎
- この本の重要な言葉なのですが、みつえさんが「わたしがぼけたから父ちゃんが現われたのなら、ぼけることも悪いことばかりではないかもしれない」と言うのですね。これは岡野さんの希望の言葉です。
- 岡野
- だんだんと認知症が進んで、ある日脳梗塞で入院し、その後グループホームに入所しました。
- 末崎
- これは入所後の作品ですが、「不穏解消の処方箋」というのがあります。
- 岡野
- 訪ねても私が分からなくて叫んだりする不穏の時と言うのがあります。そんな時、帽子を脱いで頭を見たら「ゆういちか」と言ったのですね。生まれて初めて禿げていてよかったと思った瞬間でした。
- 末崎
- みつえさんの表情がとてもいい。顔が童女のようです。みつえさんは幸せそうでだんだんと豊潤になっていくような気がします。
- 岡野
- 若い時は「しっかり者」と呼ばれ、しっかりしなくてはと気を張って生きてきたと思いますが、そういうものから解き放たれて、今はゆっくりゆっくり生きているように感じます。
- 第二部・鼎談
漫画家・シンガーソングライター 岡野雄一氏 認知症の人と家族の会京都府支部代表 荒牧敦子氏 同副代表 鎌田松代氏 コーディネーター 末崎光裕氏
- 末崎
- それでは、これまでの流れを受けて、お話を進めましょう。
- 荒牧
- 私は、昭和60年から平成17年まで3人の認知症介護を経験しました。父も義母も岡野さんの作品に重なる所がたくさんありました。岡野さんのようにうまく対応できなくて、毎日の介護の中でカーッとなったりすることがありました。
- 岡野
- 僕は読者から時々「甘い」とお叱りを受けます。
- 荒牧
- 岡野さんの本を読んでいると、お母さんが過ごしてこられた人生が見えてくるような気がします。この本のすごいところです。
認知症の母を描くことが心の癒しに

- 岡野
- マンガを描く上で、母はネタの宝庫でした。母をマンガにするということが僕にとって精神的にも安定する処方箋だったと思っています。
- 末崎
- ちょっと前までは家族が認知症ということは親戚にも言えませんでした。言わなくて閉じこもってしまうと、客観的な視点が持てないですよね。
- 荒牧
- 岡野さんは認知症のお母さんを地域にどう受け入れてもらっておられましたか。
- 岡野
- 僕は地域との結びつきが希薄な人間です。たぶん何人か同じような事情を抱える家族はあったはずですので、もっと地域の人と密にいろいろ話し合うべきでした。
- 荒牧
- 私が父の介護をしたのは介護保険制度が始まる前で、まだ認知症に対する偏見がすごくありました。それで傷つくことが結構あって、もっと認知症のことを知ってほしいと考えたのが私の活動の原点です。
- 鎌田
- 私は両親が佐賀在住で遠距離介護をしています。だからこそ近所の人たちに知ってもらわないと、と考えて、父も母もアルツハイマー病だと言いました。近所の人たちにはいろいろと面倒を見ていただきました。
地域で認知症の人を見守っていくには

- 末崎
- 全国で認知症サポーターが増えています。介護ボランティアなど、将来自分が必要になった時に世話になれる仕組みづくりに取り組んでいる市民団体もあります。
- 鎌田
- 京都では徘徊を散歩とみるようなご近所との関係が築ければいいなと思います。
- 荒牧
- 南山城村のようなお互いの顔が見える地域では、認知症の人が徘徊していても、みんなで見守ることができるようです。どこでもそうするには、もっと認知症のことを皆が勉強して知ることが大切です。
- 鎌田
- 認知症は長寿の証だと思います。岡野さんはどうお考えですか。
- 岡野
- 確かに長く生きてればこそのことです。僕は認知症より「ぼけ」という言葉のほうが好きなのですが、一日でも長く生きて、ぼけて父が現われたり、幼友達が現われたりする認知症の母を見ていて、本当に悪いことばかりではないなと思います。
第三部・弾き語り
漫画家・シンガーソングライター 岡野雄一氏

ホーム・スイート・ホーム
どんげんでんなる など
<同時開催>
「ペコロスの母に会いに行く 岡野雄一漫画展」の様子