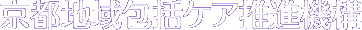- ホーム
- >
- 府民講座・イベント情報
- >
- 最期までその人らしい生活を支える在宅医療 - 府民講座レポート
地域包括ケア 府民講座レポート
最期までその人らしい生活を支える在宅医療

- 講師:仙台往診クリニック院長 川島孝一郎氏
- かわしま・こういちろう1954年山形県生まれ。北里大学医学部卒業、東北大学医学部大学院修了。1996年在宅で暮らしを守り続ける医療を目指して、仙台往診クリニックを開業。東北大学医学部臨床教授(総合診療部) 、東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープ研究教授。厚生労働省「終末期医療に関する調査等検討会」委員などを歴任。
在宅医療を支える地域包括ケア

2000年に介護保険制度が始まりましたが、国は1990年代から国民の期待に沿う形で在宅医療の制度を整備し、介護保険スタート以降は在宅医療を進める方向に大きく舵を切りました。そのことを早くから知った私は、在宅医療に本格的に取り組むため、1996年に仙台往診クリニックを設立しました。
「最期までその人らしい生活を支える在宅医療」が今日の講演テーマですが、その在宅医療を支えるのが地域包括ケアです。では地域包括ケアとは、いったい何なのでしょうか。
まずその前提として、人口構成から予測できる「治らない国・日本」という現実があります。高齢化が進んで老人が増えると、免疫力や抵抗力が弱まり、がんの発生率が高まります。一年間に亡くなる人は今約120万人ですが、2040年には約1.5倍の170万人になり、その半数はがんであるといわれています。病気が治らずに最期を迎える人の多くは「家で最期を迎えたい」と望んでいます。各種調査によると大体60%から70%がそう考えていて、がん患者では83%に達するというデータもあります。
「ピンピンコロリ」という言葉をご存知でしょうか。いつまでも健康で、大往生したいということです。多くの人がピンピンコロリを望みますが、これは誤解に基づく妄想です。ピンピンコロリは急死することに他なりませんが、そうなればそれはそれで大変ですし、急死は全体の10%程度に過ぎません。たいていの人は徐々に衰えながら、他者の支援が必要になり、やがて最期の時を迎えることになります。よりよく生きるためには、自分の体がどのように衰えていくのかをきちんと知っておく必要があります。
私たちは死ぬ前に障害者になる

そこで大事なのが医療や介護の一体的提供を含めた地域包括ケアという考え方です。30分でたどり着ける生活圏域に生活支援と介護、医療、予防、住まいの五つの柱がちゃんとあって、その中で最期まで自分の家で暮らせる。そのために医師やケアマネジャー、ヘルパーとグループホームなどの施設の医療・介護サービスをどう組み合わせていくかということです。
さて急死しない限り、私たちは死ぬ前に必ず障害者になります。では、障害を持って生きることは、果たしてそれほど惨めなことでしょうか。乙武洋匡さんは著書「五体不満足」の中で「五体が満足だろうと、不満足だろうと、幸せな人生を送るには関係ない。」と書いています。これから治らない人が増える日本にとって、これはとても大事な考え方です。
私たちは必ず歩けなくなり、食べられなくなる日が来ます。その時に大事なのが「生活機能」という言葉です。もともとWHO(世界保健機構)が2001年に障害という言葉を生活機能に置き換えることを提唱したのがこの言葉の始まりで、「生きることの全体」「私の心身だけでなく、家族・地域・国も含めた私を取り巻く環境のすべて」という意味です。地域包括ケアにとっても欠かせない言葉です。
人はどんな風に衰えるのか

さて、それではどんなふうに私たちが衰えていくのかを見てみましょう。たいていの人はまず、歩けなくなってきます。車いすに乗り、やがて寝たきりになります。人はたがいに寄り添いながら生きています。人のお世話になるのが古来の慣わしです。入居、通所など様々なサービスがありますから、胸を張って介護を受けましょう。
その次には食べられなくなります。唇やあごの力が衰えるのとカロリーの処理能力の低下の二つが理由です。また、次第に呼吸も弱くなってきます。食事や呼吸を補うには、胃瘻や人工呼吸器という選択肢があります。それらを最期の日まで連れ添う伴侶のように解釈して、楽しく生活する人がたくさんいます。つけるかどうかは、本人や家族を含めた全員の意向や患者の病状、老化の度合いを見て判断しましょう。
身体全体が衰えてくると、心臓も弱くなります。血圧が下がって、上が80を切るようになると、余命数日から一週間と考えられます。70を切ると一両日中となります。いよいよ最期の日が近づくと、体力は急速に低下します。残り少ない体力を温存するため、身体が反応して眠りにつき、多くの人は静かに息を引き取ります。眠っているということは、すべての苦痛から解放されて安らかな時を過ごしているわけですから、周囲の家族や親類縁者が勘違いして「自宅で最期を迎えたい」という本人の意思に反して、いよいよの時に救急車を呼ぶようなことがあってはなりません。
在宅療養は望めば誰でもできる

患者が望めば、今はどんな重症でも在宅療養ができます。独居で全身まひで呼吸器や胃瘻をつけていたとしても、在宅療養できる障害者総合支援法に基づく制度がすでに日本にはあります。また、昨年WHOが日本の介護保険制度を実態調査した報告書があるのですが、日本の介護は世界の五指に入るほど高い水準であることも分かりました。制度も支援体制もあるのです。
さて、在宅医療の現状はどうでしょうか。有料老人ホームやグループホームなども含む在宅死亡率は全国平均で平成17年の14.4%を底に同22年には16.1%まで高まってきました。京都府の在宅死亡率は同24年が18.8%で47都道府県中13位、京都市は19.7%で21政令指定都市中7位。実は京都は最期まで自宅で過ごしやすいところだということが分かります。私たちの6割以上がそう望んでいるわけですから、地域包括ケアで皆さんの希望に沿うような医療や介護が提供できるようさらに頑張りましょう。