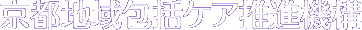- ホーム
- >
- 府民講座・イベント情報
- >
- まちで、みんなで、認知症をつつむ~共感と協働のまちづくり~ - 府民講座レポート
地域包括ケア 府民講座レポート
まちで、みんなで、認知症をつつむ~共感と協働のまちづくり~

- 講師:大牟田市認知症ライフサポート研究会代表
大谷るみ子さん - おおたに・るみこ1999年東原整形外科病院看護部長、1996年デンマーク日欧文化交流学院にて福祉を学ぶ。2001年グループホームふぁみりえホーム長、大牟田市認知症ケア研究会代表、2005年はやめ南人情ネットワーク世話人、2011年厚労省ライフサポートモデル研究事業ワーキンググループ委員
認知症をどう支えるか

大牟田市から皆さんとご一緒に認知症の人をどう支えるかを考えるためにやって来ました。やがては自分も通る道、どんな道を作ったらいいのかお話しできたらいいなと思います。前半では認知症の人の理解についてお話しします。後半は我が大牟田市が誇る認知症のまちづくりについてお話しようと考えています。
まず、大牟田市のことを少し紹介します。大牟田市は炭坑節で知られる三池炭鉱で栄えた町です。人口は一番多かった時で20万人を超えていましたが、いまは12万3千人で、高齢化率は31・1%と驚くような高さです。人口減少で若者が減り、お年寄りが増えているのです。大牟田ではすでに10年前に認知症が待ったなしの問題でした。つまり、取り組む必要がある切実な背景があったのです。
さて、認知症の人の理解についてです。認知症とは70ほどある何らかの病気が原因となって起きる脳の病気のことです。多くは物忘れや判断力の低下が起こり、日常生活や社会生活に支障をきたします。病気が原因ですから、放っておかずに早期に治療や支援を受けることが大切です。中には治療可能な認知症もありますが、根治治療薬はまだ開発中です。65才以上の4人に1人が認知症とその予備軍といわれる時代ですから、他人事ではなく私たち自身の問題としてしっかり学び、備えをしておくことが大切です。
認知症の人は何も分からなくなると誤解されていますが、実際はそうではありません。本人にとっては、今まで難なく続けてきた、「朝起きて、自分で身づくろいし、何時何分の電車に乗って…」というようなことが難しくなります。身の回りで不可解なことが起こり、どんどん不自由になっていくのです。認知症の人は混乱し、不安や恐れを感じているのでしょう。そのために焦りやいらだちが起こり、心穏やかではいられなくなるのです。
気持ちを理解し、受け止める

私たちから見ると、徘徊や被害妄想、暴力など問題と感じる行為も、認知症の人の側から見てみると、「助けて!」「何をするの?」という自分の思いがうまく言葉として伝えられず、それでも何とかしようとして、表出された思いなんだと考えられます。また、病気による症状だけでなく、薬や体調・周囲の環境などが影響していることが理解できれば、認知症の人への目線や支え方が変わってくるのではないでしょうか。
私は認知症がまだ痴呆症と呼ばれている時に「痴呆性老人とは痴呆というハンディキャップを持ちながら、その中で彼らなりに何とかしようとしている姿、あるいはそれができずに困惑している姿だ」と教えられました。そして、その方の生き方を知り、少しでもその人らしく暮らせるように支えるのがケアであるということを学びました。
私たちの役割はその方の気持ちをちゃんと理解して受け止めることです。ご本人らしさを大切にし、その人ができることについては、たとえ、失敗することがあったとしても、そばに寄り添い必要な支援をしてくれる人との絆があれば、安心できるはず。こんなことが家族や友人、地域にも理解してもらえたら有り難いと思います。
安心して徘徊できるまちづくり

ここからは大牟田のまちづくりの話です。先ほどお話ししたような事情から大牟田では実に様々なことを行ってきました。認知症のことを学んだ認知症サポーターもたくさんいますし、家族支援や物忘れ検診、物忘れ予防教室などもあります。徘徊模擬訓練がことしで10回目になり、目標である安心して徘徊できる町に近づいてきました。小中学生対象の絵本教室も開いています。
最初の年の平成14年度に一番初めにやったのは実態調査でした。市内全世帯と高齢者3千人、家族3千人の大規模な調査でした。「地域で認知症の人を支える仕組みは必要ですか」という質問に512人の人が「必要ない」「行政や病院に任せればよい」と答えました。けれども高齢化に伴う切実な問題をそのままにしておくことはできない。多くの方が「思う」と答えられました。身近な小学校校区の公民館や民生委員などのつながりや地域資源をもっと活用しようと生まれたのが私のグループホームがある校区の「はやめ人情ネットワーク」でした。一つの小学校区をモデルにして、ここが徘徊模擬訓練の発祥の地になりました。
徘徊模擬訓練は一つの校区から市内全域に広がり、全国的に広がって行きました。実際に認知症役の人に市内を徘徊してもらって、警察から小中学校や消防、タクシー会社、コンビニ、郵便局など様々なサポーターに認知症のお年寄りがいなくなったという情報が入り、みんなでそれらしきお年寄りに声をかける訓練をします。最近では社会貢献ということで事業所や行政機関が自主的に協力を申し出てこられます。徘徊模擬訓練は目的でなく手段です。その成果として、夜間でも休日でも4千か所以上に徘徊情報が届くようになりました。
絵本教室には5000人超が参加

もう一つ、実態調査で認知症を隠さず、恥じず、守り支えるという地域全体の意識を高めるには子供の時から認知症について学んだらいいのではないかと答えた方が817人おられました。そこで作ったのがこの絵本です。「いつだって心は生きている」、サブタイトルに「大切なものを見つけよう」とあります。この大切なものとは、「まちで、みんなで認知症の人をつつむ」という価値観のことです。この絵本を使って10年間、小中学校で出前授業をやっています。これまで5千人以上の子どもたちが認知症について学んでいます。子どもたちは徘徊模擬訓練にも参加します。子どもたちを交えたまちづくりは必ず成功します。子どもたちのお蔭で私たちのまちづくりも大きく進みました。
行政と地域との連携では、大牟田市が独自に養成したコーディネーターの存在が大きいです。これが核となって地域の底上げにもつながっています。この認知症コーディネーター研修は11年目に入り、2年間最大406時間学ぶ研修を85人が修了しています。このコーディネーターが専門医らと一緒に物忘れ検診や予防教室を開いたりして、地域に密着した活動を続けています。
大牟田市では「認知症、知っててあたりまえのまちをつくろう!」などをスローガンに10年間、まちづくりをやって来ました。日本一と言われますが、まだ到達度は40点、4割くらいです。それでも認知症のまちづくりを肌で感じられるところまで来ていますから、それは大きな成果だと考えています。