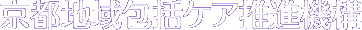- ホーム
- >
- 府民講座・イベント情報
- >
- 安らかな看取り~平穏死について考える~ - 府民講座レポート
地域包括ケア 府民講座レポート
安らかな看取り~平穏死について考える~

- 講師:東京都世田谷区立特別養護老人ホーム「芦花ホーム」常勤医師 石飛幸三氏
- いしとび・こうぞう昭和36年慶應義塾大学医学部卒。ドイツの病院で血管外科医として勤めた後、昭和47年から東京都済生会中央病院勤務、副院長などを経て平成17年から現職。主な著書に「『平穏死』のすすめ」「『平穏死』という選択」など。
なぜ「『平穏死』のすすめ」を書いたのか
「『平穏死』のすすめ」という本を三年半前に出版しました。「平穏死」という言葉は、単に穏やかにという感覚的な言葉ではありません。老いは誰にも訪れます。日本は今や世界一の高齢化社会。団塊の世代の高齢化がそれに拍車をかけています。ところが、医療の現場では延命治療があるならどこまでもやらなければいけないという強迫観念があります。一度しかない人生をしっかり生きて、その最後をどう締めくくるか、一人一人が考えなければいけない時代が来ている。そんな思いで「『平穏死』のすすめ」を書きました。

私の勤務している芦花ホームは、東京の西に位置する世田谷区にあります。ここに来るまで私は急性期病院に半世紀おりました。そこで外科医として夢中で病気と闘ってきました、それが、自分が還暦を迎えたころに少し変わりました。いずれは自分にも最終章が来る。どう自分の人生を締めくくっていくのか。人生の最後に医療はどうかかわるべきか。そう考えて芦花ホームの常勤医になりました。行ってみてよかった。今日はそこでどういうことが起こり、その後それがどうなっていったかを皆さんと一緒に考えてみたいと思います。
強迫観念が進めた胃瘻などの延命措置
芦花ホームに来られた方は、確実に老化の坂を下って行かれます。食事介助でもう一口が仇となり、誤嚥性肺炎になり、病院に運ばれるケースがあります。反射機能の衰えから、本来は食道を通って胃に行くべき食べ物や飲み物が気管支から肺に入ってしまうのです。病院に行けば、手っ取り早い誤嚥の処置は、へその上に穴をあけ経管栄養剤を直接胃に入れるようにする胃瘻です。芦花ホームでも胃瘻を付けられた人がどんどん増えてきた。私が行ったとき16人だったのが、あっという間に20人を超えました。

胃瘻を付けた人で元気になった人がいない、とは言いません。ただ、ホームでやっと生活していたのに押さえつけられて、無理やり点滴を続けられると、老いの階段を二段も三段も下ってしまいます。まして、食べる楽しみを奪われたら頭はさらに混乱します。しかも、おなかがいっぱいなのに本人はそう意思表示できない。一定量の経管栄養剤を決まった時間に入れるやり方では、胃から逆流した栄養剤を誤嚥して肺炎になることもあるのです。
芦花ホームでは、開設間もない二十年ほど前に入所者が誤嚥性肺炎で亡くなる事故があり、家族が病院を訴えて裁判になりました。それ以来、職員の間にはいったい自分たちはどうしたらいいのかという戸惑いが広がっていました。また、様々な延命治療法が出てくる中で、保護責任者遺棄致死罪の強迫観念もあります。やっておけば責任追及されないという理由から、本人の意思とは関係なく胃瘻などの延命処置が行われていました。
誤嚥性肺炎が減り、自然死が増えた
入所者のために何が一番いいのか。しっかり本質を見つめれば、家族と施設職員の目標、目的は本来一緒のはずです。ボタンの掛け違いを何とかするために家族と職員で勉強会を始めたのが5年前。やってよかった。皆さん真剣でした。家族の中から方法があれば何が何でも延命をやらなければいけないというのはおかしいという本質的な声が出てきました。

二つのきっかけがありました。平成12年に三宅島が噴火して島の認知症のおばあさんが芦花ホームに避難してこられました。5年して誤嚥性肺炎で病院に運ばれ、島にいる息子さんのところに医師から胃瘻を勧める電話がありました。息子さんは「島ではそんなことはしない。食べられなくなったら最後は水だけで家族に見守られ最期を迎えるのです」と答えたのです。
もう一つは八歳年上の姉さん女房がアルツハイマーで入所されたご主人のケースです。戦争中にお母さんと妹が世話になった大切な奥さんです。芦花ホームにきて間もなく誤嚥性肺炎になったのですが、医師から胃瘻を勧められたご主人は「今は自分の事も分からない女房だが、恩を仇で返すことになるからしない」と断ったのです。奥さんは芦花ホームに戻り、ご主人は施設に足を運んで、奥さんの食事介助を続けられました。施設の職員と食事介助を一緒に続け、この奥さんはそれから一年半、食事を続けることができました。
自慢できるデータがあります。私が芦花ホームに勤務してから誤嚥性肺炎の件数が減って、自然死の件数にとって代わっています。救急車騒ぎががぜん減少しました。入院先の病院で死ぬ人の数も減りました。若い女性介護士が看取りをするようになってこんなことを書きました。「大切なのは死の瞬間だけではない。入所者がどう生きたか。それが最後に結実する」と。
人生の最終章に医療をどう活用するか

高齢化社会とは、自然の摂理に対する医療の意味をしっかり考えなければならない時代のことです。自分のたった一度の人生、その最終章に医療をどう活用するのかを自分で考えなければならない時代がやってきています。
最後に一つの例を挙げて締めくくりとします。アルツハイマーで入所した元タクシー運転手のケースです。発症から20年後、徘徊する力もなくなった頃、誤嚥性肺炎で病院に運ばれました。医者からは胃瘻を付けるよう勧められたのですが、奥さんも介護主任もホームで食事をとる生活を続けることを主張して、病院から連れ帰ったのです。医者の前で本人が「食べたい」と言ったのが決め手でした。さすがに帰ってから三日間は何も口にしませんでしたが、ウナギが好物だというので、うな丼をペースト状にして食べさせたら、おいしそうに食べたのです。それからしばらく元気を取り戻して、亡くなる2日前にはご夫婦の結婚記念日をお祝いしました。
このサプライズパーティーを準備してくれたのは、非番も含めた介護士7人と看護師5人です。本当にうれしかった。若い人たちの感覚は我々の思わぬところまで進んでいます。私はこれなら日本はまだまだ大丈夫だと考えています。