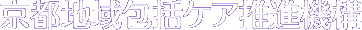- ホーム
- >
- 府民講座・イベント情報
- >
- なるな寝たきり、つくるな寝たきり~住民主体の介護予防~ - 府民講座レポート
地域包括ケア 府民講座レポート
なるな寝たきり、つくるな寝たきり~住民主体の介護予防~

- 講師:茨城県立医療大学 名誉教授
茨城県立健康プラザ 管理者 大田仁史氏 - おおた・ひとし昭和37年東京医科歯科大学医学部卒。伊豆逓信病院副院長を経て、平成7年茨城県立大学教授、同8年同大学付属病院長。平成17年度から茨城県立健康プラザ管理者。日本リハビリテーション医学会専門医・評議員、全国地域リハビリテーション研究会代表世話人などを歴任。
高齢化社会は「予防」がキーワード
本日は、私たちが力を入れているシルバーリハビリ体操事業を紹介します。今の時代、高齢化社会は「予防」がキーワードです。介護が必要になる状況にできるだけならないようにするとともに、たとえそうなってもできるだけ進行させない努力が必要だと思います。そのためにシルバーリハビリ体操は、大きな効果を発揮します。
茨城県立健康プラザでは、特定健診を受けた5300人を対象に平成20年から10年間で医療・介護費がどれくらいかかるかという追跡調査を続けています。その中間報告を見て驚きました。40歳から64歳までも医療・介護費は少しづつ伸びているのですが、65歳になると急激に上昇する。それも驚きでしたが、この時点ではまだ団塊の世代が65歳になっていませんでした。団塊世代が続々と65歳以上になったら、現在起きているようにどれくらいになるのか見当もつきません。結論から言うと、やはり予防しかないのです。
先の東日本大震災では、茨城県でもたくさんの人が津波で亡くなりました。明るいニュースは、我々が養成したシルバーリハビリ体操指導士が避難所に入ってくれて、ボランティアとしてお年寄りに体操指導をしてくれたことです。県内各所で自主的に、連絡を取り合いながら活動してくれました。

一般住民がある考え方を共有して、ネットワークを持ちながら自助・共助できる仕組みをソーシャルキャピタルといいます。震災はいろんな教訓を残してくれましたが、お年寄りが多い地域でサービスの足りないところには同じ仕組みが活用できるなと思いました。
「団塊」の津波にどう備えるか
さて、本論に入ります。団塊の世代の問題です。津波は水の塊でいつ起きるかわかりませんが、団塊世代は人の塊ですから、いつ来るか分かります。対策を取ろうと思えば、取れるのです。対策は二つあります。一つは団塊世代を津波に例えると、堤防を高くすることです。制度を整えて、サービスを増やすことです。もう一つは団塊の世代の健康寿命を延ばしてもらうことです。団塊の世代の一部が健康で長生きしてもらえれば、団塊の津波を崩すことができます。

団塊の世代以上が問題なのですから、まずはこの世代間による自助・互助が基本です。自分の事は自分でしっかりやるという気持ちを持つこと。それだけでなく、他人のことを思いやることもしっかりやらねばなりません。その上で、自分たちだけでできないことは若い人の力を借りる。これが共助・公助、先ほどのソーシャルキャピタルにもつながってくる話です。
具体的な介護予防の話ですが、二つの線を作ってみました。一つ目は「守るも攻めるもこの一線」という線で、寝ている状態と座っている状態の間にある線です。座るということは、人の尊厳にかかわるトイレに行けることにつながります。解剖学的にいうと、寝ているというのは骨盤が寝ている。座っているのは骨盤が立っている状態です。座っていれば、トイレに行ける可能性が出てくるのですが、寝ているとその可能性はありません。それだけでなく、寝ていると筋力も低下し、内臓の働きも悪くなります。

二番目の「越えねばならぬこの一線」というのは外出です。外出は大事です。高齢者が外へ出て、1日に家族以外の3人に会って話をすれば認知症にならないといわれるほどです。この反対が閉じこもりですが、本人だけでなく家族も「外出して、転んで骨折して、寝たきりになったらどうするの」と心配して、逆効果になっていることがあります。
最後まで人間らしい生き方をするには

体の悪い高齢者がどうすれば外出できるか。一般的には車いすを想定します。介護する側から見ると、軽い介助で立ち上がってくれると助かります。立ち上がって、何かにしがみついて少しの間立っていてほしい。2、30秒でも立っていてくれると、慣れてくればパンツの上げ下ろしができる。これができると、飛行機にも乗れます。背もたれなしで用が足せて、車いすで使える洋式トイレがあれば、どこへでも行けます。
これだけのことです。最後まで人間らしい生き方をするには、自分で体を鍛えて、自分で自分を守ることです。そのためには、どこでも、一人でもできるシルバーリハビリ体操をやってくださいという事業を私たちは進めています。シルバーリハビリ体操は、ラジオ体操などと異なり、何のためにどこの筋肉を使って、どの関節をどう動かしているか、など一つ一つの体操が明確に体系化されています。これは趣味のスポーツではありませんから、行政がしっかりサポートしないといけません。
事業効果がはっきり見えてきた
私たちは、シルバーリハビリ体操指導士の養成事業を平成17年から始めました。住民運動は活動家を選んで育て、組織してフォローするという四つがそろわないとうまくいかない。幸い、今年八月時点で茨城県44市町村中22市町村に計105人の1級指導士が誕生しました。3級までの指導士全体では計5672人います。平成24年度には、これらの指導士が県内各所で28015回、シルバーリハビリ体操教室を手弁当で開き、お年寄り456000人が参加しました。

事業効果もはっきり見えてきました。指導士の数が増えると、軽度の要介護のお年寄りの数が減る。経年的に事業を続けると、軽度の要介護が減るということも分かりました。他府県との比較で見ても、茨城県は要支援1から要介護1までの人口割合が全国最下位レベルにあります。
私たちが直面している超高齢化社会は、自らが学び、力をつけ、自らが社会に役立つ行動を起こし、世代を超えた互助・共助の精神で官民一体となって乗り切るべきものです。行政や専門家だけに任せたら、介護が必要な寝たきりのお年寄りは益々増え続けます。シルバーリハビリ体操で介護予防が本当にできるのかと問われれば、私は「YES,WE CAN」と答えたいと思います。